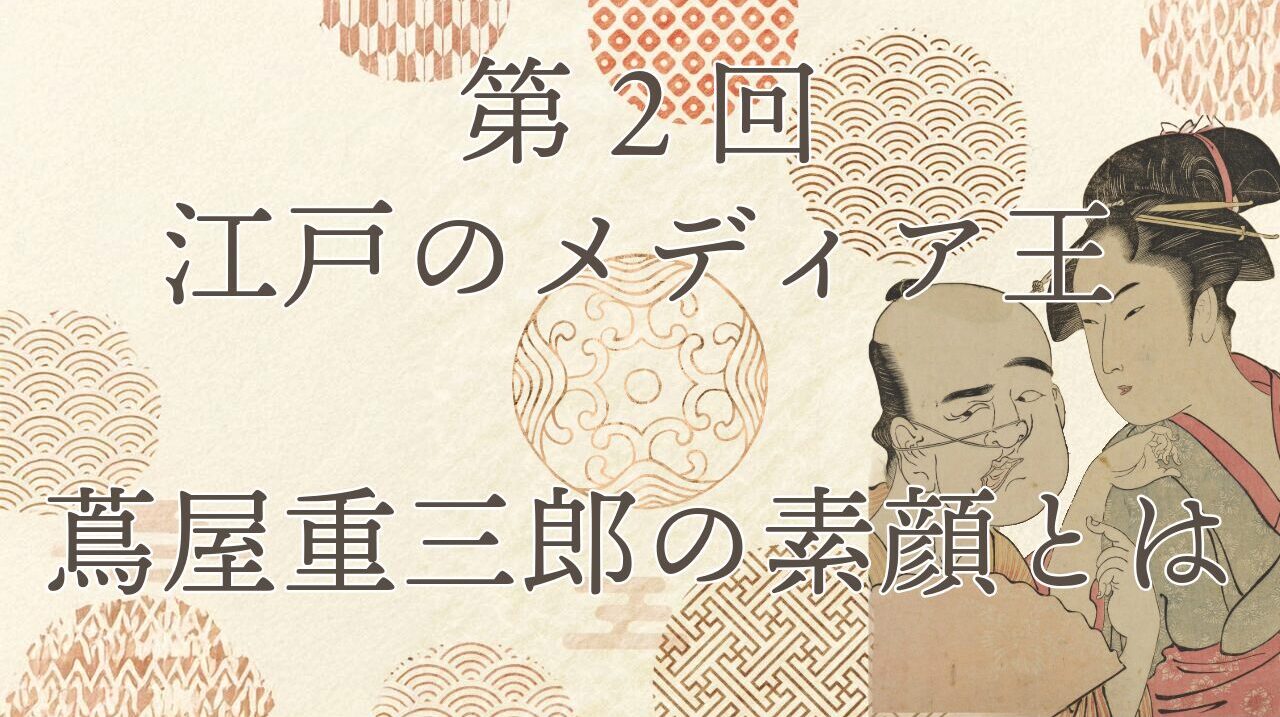
吉原細見の版元になって評価を高めた蔦重(蔦屋重三郎)は、人気絵師による華やかな多色刷り絵本など、吉原を舞台にした作品を次々に発表し、ますます人気者となりました。そして常に流行に敏感で巧みな話題づくりをして商売を拡大し、人気作家や絵師を味方につけながら、黄表紙や狂歌本など新しいジャンルの出版物で大ヒットを飛ばしていきます。
蔦屋重三郎のべらぼうな生涯に迫る連載第2回では、彼のビジネス手腕を物語る様々な取り組み、プロデューサーとして作家の才能を見出す力に迫ります。
目次
耕書堂の経営基盤を固める
吉原大門口近くの茶屋の軒先を借りて耕書堂を経営していた蔦重は、安永6(1777)年、心機一転、数軒隣に独立した店を構え、耕書堂の経営基盤の強化のため、二つのジャンルに参入しました。
![浅草庵 作『画本東都遊 3巻』、享和2年 [1802] 、国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2533327
蔦屋重三郎が経営する書店「耕書堂」](https://www.tokyo-shiki.co.jp/wp-content/uploads/2025/02/耕書堂(通油町)-543x720.jpg)
浅草庵 作『画本東都遊 3巻』、享和2年 [1802] 、国立国会図書館デジタルコレクション
https://dl.ndl.go.jp/pid/2533327
蔦屋重三郎が経営する書店「耕書堂」
常に流行の最先端をゆく
一つは、「富本節の正本」の刊行です。富本節は、当時、流行していた浄瑠璃の流派です。浄瑠璃というのは三味線の演奏にあわせて太夫が詞章(語り)をする音楽ですが、その詞章を記したものが正本(しょうほん)です。この頃、富本豊前太夫という美声の人気太夫が登場し、富本節がブームとなりました。そして豊前太夫が江戸のあちこちに稽古場を開くと江戸庶民が富本を習いたいと押しかけ、正本や稽古本の需要が高まりました。
この流行にいち早く目を付けた蔦重は、富本豊前太夫と専属出版の契約を結び、蔦屋版の正本や稽古本を刊行します。格式ある浄瑠璃の正本を吉原の本屋が手掛けたことが話題となって売れ行きは上々。富本節正本や稽古本の刊行は、蔦屋の経営基盤の一つとなりました。
](https://www.tokyo-shiki.co.jp/wp-content/uploads/2025/02/富本節正本-503x720.jpg)
中村重助 作 『夫婦酒替奴中仲』、安永06年[1777]、東京大学教養学部国文・漢文学部会所蔵
※一部切り抜きによる改変
富本節正本
手堅い商品もしっかりと
もう一つ、蔦重が経営の柱としたのが「往来物(おうらいもの)」の刊行です。江戸時代中後期には庶民の教育機関である寺子屋が著しく増加しましたが、その寺子屋での手習いの教科書として使われたのが往来物です。この頃には、農村用の「農業往来」、商人向けの「商売往来」、武士向けの「武家往来」など様々な種類が刊行されていました。蔦重も和算の教科書『利得算法記(りとくさんほうき)』や女子用の『女今川艶紅梅(おんないまがわつやこうばい)』など多数を刊行しました。
富本節正本や往来物は爆発的に売れるものではないものの、一定数の需要があり、安定した利益を見込める商品です。蔦重はこうした息の長い商売にもしっかり取り組み、確実に経営基盤を強化していきました。
草双紙と黄表紙の出版を開始
蔦重は新たな試みとして、当時流行の戯作(通俗文学)の出版に手を広げます。特に「草双紙(くさぞうし)」とその一種である「黄表紙」の出版です。
草双紙とは、仮名書きで絵入りの娯楽本のことで、表紙の色によって「赤本」「黒本」などと呼ばれていました。「赤本」は『桃太郎』などの童話中心の子ども向けのもの、「黒本」は歴史物・伝記物・歌舞伎の筋書きなどをテーマにした大人向けのもので、挿絵を主体とした誌面なので、手軽に読むことができました。
黄表紙の誕生
安永4(1775)年、草双紙の歴史を変える大ヒットが生まれます。それが、恋川春町が絵と文を手掛けた『金々先生栄花夢』です。版元は鱗形屋孫兵衛。田舎者の金々先生こと金村屋金兵衛が一旗揚げようと都に出て栄華と没落を体験しますが、それは全て夢の中の話だったという「落ち」が江戸っ子に大受けして評判となりました。
こうした当時の風俗や世相を面白おかしく風刺した作品が、草双紙を大人向けの娯楽に一変させて「黄表紙」というジャンルを生み出し、黄表紙が新たな出版の主役となっていきました。
![恋川春町 戯作『吉原大通会 : 3巻』、天明4年[1784]、国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/9892509](https://www.tokyo-shiki.co.jp/wp-content/uploads/2025/02/吉原大通会黄表紙-536x720.jpg)
恋川春町 戯作『吉原大通会 : 3巻』、天明4年[1784]、国立国会図書館デジタルコレクション
https://dl.ndl.go.jp/pid/9892509
※一部切り抜きによる改変
実際に黄色い表紙であることがわかる
行動力の蔦重 今度は作家をプロデュース
蔦重もこの機を逃さず黄表紙の出版に進出し、安永9(1780)年には、8冊の黄表紙を出版しました。そのうち3冊は朋誠堂喜三二(ほうせいどうきさんじ)の作品です。朋誠堂喜三二は戯作のペンネームで、本名は平沢常富といいます。秋田藩の江戸留守居役を務める武士ですが、「宝暦の色男」を自称して吉原に頻繁に出入りし、蔦重とも関係を深めて、耕書堂の主力作家として蔦重の出版活動を支えていきます。
もう一人、黄表紙などの戯作出版において、蔦重の重要なパートナーとなったのは山東京伝(さんとうきょうでん)です。山東京伝は浮世絵師・北尾重政から絵画を学び、北尾政演という名で挿絵や錦絵を手掛けていましたが、天明5(1785)年、蔦重のもとで出版した、黄表紙の傑作『江戸生艶気樺焼(えどうまれうわきのかばやき)』が大ヒットし、戯作者としての地位を不動のものとしました。
天明狂歌の流行と蔦重の躍進
版元としての活動が軌道に乗るなか、天明3(1783)年、蔦重は耕書堂の本店を日本橋通油町に移します。当時の日本橋は江戸有数の豪商が集まる経済と情報の中心地で、江戸の出版界を代表する地本問屋が軒を連ねる一等地でした。吉原から超一流の店が並ぶ日本橋に進出することは、蔦重が一流の地本問屋の仲間入りを果たした事を意味します。このとき蔦重は33歳。吉原大門口の書店開業からわずか10年ほどのことでした。
狂歌ブームの始まり
天明年間(1781~1789年)、爆発的な流行を見せたものに「狂歌」があります。
狂歌とは、五七五七七の和歌の形式を保ちながら、わかりやすい言葉を使って、日常生活の機知や滑稽さを盛り込んだ短歌です。格調高い和歌に対して、世俗的な洒落や皮肉を面白おかしく詠む遊びで、記録を取らずにその場で読み捨てられるのが暗黙のルールでした。
このルールを破って、天明3年に『狂歌若菜集』『万載狂歌集』という狂歌集が出版されると、江戸の狂歌人口はうなぎ登りに増加しました。そして、「連」と呼ばれるサークルが多数生まれたり、狂歌会が各地で開かれたりするようになり、「天明狂歌」と呼ばれる狂歌ブームが巻き起こりました。
文化サロンの結成
蔦重もこの波に乗り遅れることなく、狂歌集の出版に乗り出します。蔦重は「蔦唐丸」という狂名を名乗り、自らも狂歌師として「吉原連」に属すだけでなく、様々な連に出入りしながら、狂歌界の中心人物との交流を深めていきました。
蔦重が特に親しくしていたのが、「狂歌三大家」の一人である四方赤良(よものあから)こと大田南畝(おおたなんぼ)でした。蔦重は南畝をしばしば吉原に招き、恋川春町、朋誠堂喜三二、北尾政演、喜多川歌麿などが集まる文化サロンを組織し、人的ネットワークを築いて、歌会で詠まれた狂歌を次々に書籍化していきました。
![恋川春町 戯作『吉原大通会 : 3巻』、天明4年[1784]、国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/9892509](https://www.tokyo-shiki.co.jp/wp-content/uploads/2025/02/吉原大通会-720x526.jpg)
恋川春町 戯作『吉原大通会 : 3巻』、天明4年[1784]、国立国会図書館デジタルコレクション
https://dl.ndl.go.jp/pid/9892509
※一部切り抜きによる改変
下段左から2番目が蔦唐丸(蔦屋重三郎)
喜多川歌麿の誕生
天明6(1786)年を境に狂歌ブームが下火になると、蔦重は狂歌と浮世絵を組み合わせた『狂歌絵本』という新ジャンルを開拓します。
狂歌絵本で才能を開花させたのが喜多川歌麿です。この頃の歌麿はまだ無名の新人でしたが、蔦重は歌麿の才能を見抜き、自分の店に住まわせて面倒を見るなどして、耕書堂の専属絵師のような形で登用しました。歌麿の狂歌絵本のなかで、特に芸術性の高い挿絵が評価されたのが『画本虫撰(えほんむしえらみ)』です。虫と植物を題材として絵に狂歌を添えた多色刷りの狂歌絵本ですが、歌麿の卓越した観察眼による細密で写実的な描写が読者を驚かせました。
これに手応えを感じた蔦重は、歌麿の絵で『潮干のつと』『百千鳥狂歌合』という狂歌絵本の名作を立て続けに刊行。歌麿を一流の絵師に育てていきました。

喜多川歌麿 作 蔦屋版の狂歌絵本『潮干のつと』、寛政元(1789)、耕書堂蔦屋重三郎、国立国会図書館デジタルコレクション
https://dl.ndl.go.jp/pid/1288344
※一部切り抜きによる改変
36人の狂歌師が歌を寄せた。「潮干のつと」は潮干狩りのみやげという意味。
文 鈴木悦子
あとがき
戦国時代というのは、『既得権の打破』という目的意識のもと世の中が動いていて、商売においても『楽市楽座』による自由経済が推進されていました。しかし、蔦屋重三郎が生まれた江戸時代中期になると、米価の下落により武士階級が困窮し、幕府が市場を統制するため商業者の組合化(株仲間)が進められ、商いへの新規参入が厳しく制限されるようになっていました。
そのような状況の中で、持ち前の行動力と政治力を駆使し商いの権利を勝ち取り、独自のアイデアと目利きで次々に新機軸を打ち出し成功を収めた蔦屋重三郎という人物は、まさに驚愕に値します。
さて、蔦屋重三郎の物語もいよいよ佳境を迎えます。歌麿のプロデュースを成功させ、栄華を極めた蔦重。しかし、時代の大きなうねりが彼の商売人生を絶体絶命の危機へと追い込みます。果たして、蔦重はこの危機を乗り越えることができるのか?
次回の更新もお楽しみに!
関連記事
主な参考文献
・中公ムック歴史と人物21『蔦屋重三郎 江戸文化の仕掛け人』中央公論新社
・NHK大河ドラマ 歴史ハンドブック『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~<蔦屋重三郎とその時代>』NHK出版
・TJMOOK『大河ドラマ べらぼう~蔦重栄華乃夢噺』蔦屋重三郎とその時代』宝島社 監修:鈴木俊幸
・台東区公式チャンネル【台東区中高図書館郷土・調査室】企画展関連講演会「吉原の本屋 蔦屋重三郎」講演:鈴木俊之教授
・台東区公式チャンネル【2025放送 大河ドラマの主人公を先取り】講演会「若き日の蔦屋重三郎と吉原」
https://www.youtube.com/watch?v=wVozVHwPTmw&t=2330s
