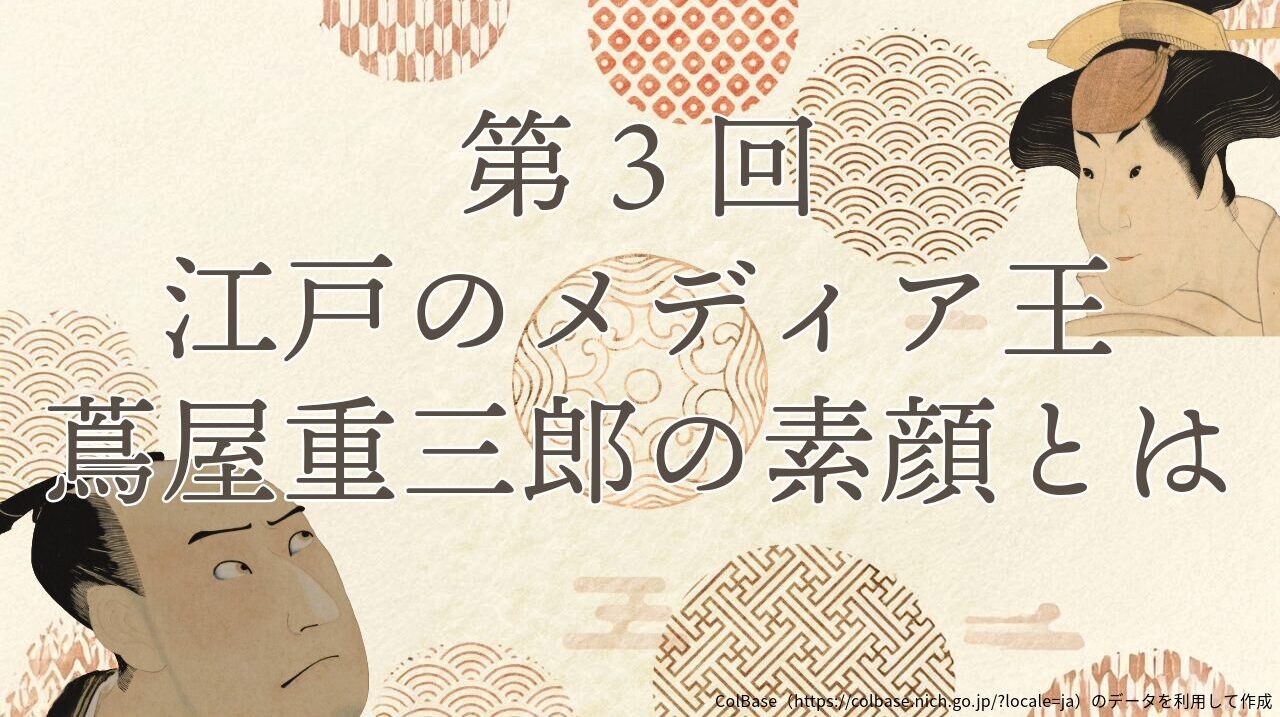
黄表紙と狂歌本の販売で快進撃を続ける蔦重(蔦屋重三郎)を中心に、盛り上がりを見せていた江戸の出版界でしたが、老中・松平定信による寛政の改革が進むと厳しい弾圧にさらされます。逆風にもめげずに蔦重は新機軸を次々に発表しますが、彼の周囲の文人たちに厳しい処罰が下され、やがて蔦重も処罰されます。そんななか蔦重は、さらなる新しい人材を開発し、新たな表現方法に挑戦していきますが、道半ばにして病に倒れついに最期を迎えます。
蔦屋重三郎のべらぼうな生涯に迫る連載最終回、斬新な企画と人間的な魅力で多くの芸術家と繋がりを持ち、多くの芸術家を世に送り出し、江戸出版界を牽引し続けてきた蔦重の47歳の最期を見ていきましょう。
目次
寛政の改革に抗して新機軸を打ち出す蔦重
天明7(1787)年、江戸幕府の内部で政権交代が起きました。老中として権勢を振るっていた田沼意次が失脚し、松平定信が老中に就任したのです。定信は、幕政から田沼派を一掃し、天明の大飢饉を始めとする天災地変で荒廃した農村の復興、幕府の財政難の解消を目指して、幕政の改革に着手します。
田沼の賄賂政治への反省から、武士には質素倹約を求めるだけでなく、文武の鍛錬を奨励し、学問や武芸に優れた人材の登用を積極的に進めました。町人には贅沢品の取り締まりや風俗の規制などをかけました。こうした厳しい引き締めに人々は息苦しさを感じ、政治への不満が高まっていきました。
常に流行の最先端をゆく
こうした世相を敏感に感じ取った蔦重は、寛政の改革を揶揄する黄表紙を世に送り出します。天明8(1788)年、蔦重は朋誠堂喜三二・作、喜多川歌麿・挿絵の『文武二道万石通』を出版。この作品は、間抜けな武士が文武奨励策に慌てふためいて武芸や学問に励むが、失敗を繰り返す姿を面白おかしく茶化したものでした。この政治風刺が江戸市民から絶賛され、草双紙売りが市中を売り歩くほどのベストセラーになったといいます。
![朋誠堂喜三二 戯作 『文武二道万石通 : 3巻』、天明8年[1788]、 国立国会図書館デジタルコレクション
※一部切り抜きによる改変
寛政の改革への風刺作品として「古今未曽有の大流行」となった](https://www.tokyo-shiki.co.jp/wp-content/uploads/2025/03/0260-0006013-0019-720x529.jpg)
朋誠堂喜三二 戯作 『文武二道万石通 : 3巻』、天明8年[1788]、 国立国会図書館デジタルコレクション
https://dl.ndl.go.jp/pid/9892612
※一部切り抜きによる改変
寛政の改革への風刺作品として「古今未曽有の大流行」となった
翌年、恋川春町・作『鸚鵡返文武二道』が蔦屋から出版されます。これも政治を風刺するもので、タイトルにある「鸚鵡返」も前年に発刊された「文武二道万石通」の後編であることを表すものでした。こちらも同じく刊行してすぐに大ヒットし、15,000部以上も売れたといいます。
![恋川春町 作『鸚鵡返文武二道』、寛政元年 [1789]
東京都立図書館
※切り抜きによる改変
初版が売切れ、増刷もかかり15,000部も発行された](https://www.tokyo-shiki.co.jp/wp-content/uploads/2025/03/digidepo_9892612_0010-720x563.jpg)
恋川春町 作『鸚鵡返文武二道』、寛政元年 [1789]、東京都立図書館
https://archive.library.metro.tokyo.lg.jp/da/detail?tilcod=0000000005-00186193
※一部切り抜きによる改変
初版が売切れ、増刷もかかり15,000部も発行された
恋川春町と朋誠堂喜三二への弾圧
さっそく幕府は、政治風刺の黄表紙に対して断固とした処置をとりました。まず、この2作品を発禁処分にし、武士出身の作家二人に圧力を掛けます。駿河国小島藩の武士だった恋川春町は出頭を命じられショックを受けて隠居し、三カ月後に死去。病死とも自殺ともいわれています。また秋田藩の御江戸留守居役だった朋誠堂喜三二も、藩主から叱責を受けて戯作界から身を引かざるを得なくなり、こののち二度と黄表紙の創作に手を染めることはありませんでした。
政治を風刺した黄表紙は、爆発的な売れ行きを記録しましたが、蔦重は、耕書堂の主力として活躍した喜三二と春町を失いました。
山東京伝と蔦重が処罰される
松平定信は寛政2(1790)年、出版統制をさらに強化し、時事ネタ、風刺、好色、華美なものの出版が禁止されました。
そんな統制に抗って、蔦重と山東京伝は翌年3冊の洒落本を刊行します。洒落本とは、吉原などの遊里を題材とした小説で、小型の形状が蒟蒻に似ていたことから、「蒟蒻本」ともいわれています。「通」という美意識を主題に、遊女と客の駆け引きを描写したり、通人ぶる野暮な客を茶化したりする内容でした。
洒落本3部作はただちに絶版となり、作者の京伝は手鎖50日の刑(両手首に手枷をはめられて自宅で謹慎する)、版元の蔦重は身代半減(財産の半分を没収)という重過料の罰を受けました。

歌川豊国 画 『山東京伝の見世』、18世紀、東京国立博物館
https://colbase.nich.go.jp/collection_items/tnm/A-10569-2140
山東京伝は京橋で煙草入れの店も経営していた。右奥が京伝。
「美人大首絵」ブームと様々な才能の発掘
処罰を受けた蔦重は、新たな浮世絵の出版で巻き返しを図ります。
浮世絵のなかでも複数の色版を重ねる多色刷りの木版画は「錦絵」と呼ばれ、宝暦年間(1751~1764)以降に大流行しました。錦絵で天明年間の美人画において人気を博していたのが鳥居清長です。描かれる女性は小顔で8頭身のすらりとした長身の全身画で「清長美人」と呼ばれ、『風俗東之錦』や『美南見十二候』は名作として高く評価されました。
こうしたなか台頭してきたのが、喜多川歌麿の「美人大首絵」です。

喜多川歌麿 画『婦女人相十品・ポッピンを吹く娘』、18世紀、東京国立博物館
https://colbase.nich.go.jp/collection_items/tnm/A-10569-546
蔦重は無名時代から支えてきた歌麿を抜擢して美人大首絵という新しい表現にチャレンジします。大首絵とは人物の上半身を描いたもので、もともと歌舞伎役者を描く役者絵で用いられた形式でしたが、蔦重と歌麿は清長の美人画との差別化を図るため、顔をアップに描くことで豊かな表情や現実感を表現した大首絵の美人画を世に出したのです。またモデルは市井の看板娘など実在の女性を描かせることで、江戸っ子の購買意欲を駆り立てました。こうして歌麿の斬新な美人大首絵はたちまち話題となり、江戸市中を席巻します。
役者絵で葛飾北斎を起用する
蔦重は歌麿とタッグを組んで美人画の黄金時代を築く一方、役者絵にも進出します。まず初めに起用したのが勝川春朗です。勝川春朗は、のちに浮世絵界の巨匠と言われる葛飾北斎のことです。春朗は蔦重のもとで狂歌絵本や黄表紙の挿絵を描いていましたが、寛政3(1791)年に役者絵を刊行。役者絵を8点ほど世に出したあと、3年後には刊行をやめています。北斎が全盛を迎えるのは蔦重が没してからのことです。
謎の新人絵師・東洲斎写楽を世に送り出す
寛政6(1794)年5月の歌舞伎興行の際、蔦重は東洲斎写楽の「役者大首絵」を28枚同時に売り出しました。出演する役者の宣伝用ブロマイドのようなものです。写楽の華々しいデビューは江戸の人々に強烈なインパクトを与えました。役者を格好良く華やかに描くことが定番だったこれまでの役者絵の常識を破り、顔の輪郭や目鼻立ちを誇張し、役者の個性を際立たせるのが写楽の役者絵のスタイルでした。
蔦重の話題作りは成功をおさめ、写楽の役者絵は大きな注目を集めますが、その画風は賛否両論を巻き起こし、その後は徐々に精彩を欠き、売り上げも減少していきました。そして寛政7(1795)年の初め、写楽は忽然と姿を消してしまいます。
![東洲斎写楽 画『三代目大谷鬼次の江戸兵衛』、寛政6年[1794]、東京国立博物館、重要文化財](https://www.tokyo-shiki.co.jp/wp-content/uploads/2025/03/A-10569-471_E0128764-467x720.jpg)
東洲斎写楽 画『三代目大谷鬼次の江戸兵衛』、寛政6年[1794]、東京国立博物館、重要文化財
https://colbase.nich.go.jp/collection_items/tnm/A-10569-471
曲亭馬琴と十返舎一九の才能をいち早く認める
写楽が去ったあと、蔦重は曲亭馬琴と十返舎一九という新しい人材を発掘しています。曲亭馬琴は寛政3(1791)年から耕書堂の手代として働き、黄表紙などを執筆。十返舎一九は寛政6(1794)年から蔦重の食客となり、耕書堂の仕事を手伝いながら、『心学時計草』などの黄表紙を書いています。のちに『南総里見八犬伝』(曲亭馬琴)、『東海道中膝栗毛』(十返舎一九)という大ベストセラーを生み出した二人の才能をいち早く認めて育てたのが蔦重でした。
不屈の挑戦を続ける晩年の蔦重
洒落本の出版による処罰で経営的な苦境に陥った蔦重ですが、次の時代を見据えて着々と手を打っていきました。寛政の改革によって学問が奨励され、学術書の需要が高まることを見越した蔦重は、書物問屋仲間に加入しています。書物問屋とは、史書・儒学書・漢籍などの学術書や専門書を扱った本屋のことです。書物問屋仲間に加入したのは、学術書などの新たな流通手段を取得するとともに、上方(関西方面)への販売ルートを確保する目的もありました。
寛政7(1795)年、蔦重は伊勢松坂に出向いて国学者の本居宣長を訪問しています。宣長の著作『手まくら』(『源氏物語』の補作)を江戸で販売するのが目的です。この年、『手まくら』のほか宣長の2冊の著書を江戸で販売していますが、これが蔦重の最期の大仕事となりました。
47年の生涯を閉じる
寛政8(1796)年の秋、蔦重は脚気を患って病床に伏します。脚気とはビタミンB1不足によって起きる病気です。当時の江戸の白米偏重の食生活が原因で、「江戸わずらい」といわれました。病状は日に日に悪くなり、翌年の5月6日、蔦重は他界しました。享年47歳。江戸出版界に新しい風を吹き込み、多くの芸術家を世に送り出し、逆境をものともせず、時流を読んで、人々をあっと言わせる作品を生み出していった江戸のメディア王・蔦屋重三郎の静かな最期でした。
文 鈴木悦子
あとがき
3回に渡ってお送りしてきました蔦重のべらぼうな生涯、いかがだったでしょうか。
世の中の流行りに敏感で様々なアイデアを形にしていく姿は、我々も見習わなければならないですね。
輝く才能を発掘する力とそれをプロデュースしていく力。これらの要素が相まって、蔦重は成功し、文化の発展に寄与しました。
蔦屋重三郎がいなければ、江戸自体の浮世絵、黄表紙文化は全く違った形になっていたでしょう。
我々も数々のご相談をうける中で、デザイナーや作家様とのやり取りも増えました。
東京紙器も蔦屋重三郎のごとく、綺羅星のような才能を発掘し、世の中に発信していくお手伝いをしていきたいと思っています。
令和の蔦重足るべく、「Ideaを形に。」していきます!
関連記事
過去の連載はこちらから
主な参考文献
・中公ムック歴史と人物21『蔦屋重三郎 江戸文化の仕掛け人』中央公論新社
・NHK大河ドラマ 歴史ハンドブック『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~<蔦屋重三郎とその時代>』NHK出版
・TJMOOK『大河ドラマ べらぼう~蔦重栄華乃夢噺』蔦屋重三郎とその時代』宝島社 監修:鈴木俊幸
・台東区公式チャンネル【台東区中高図書館郷土・調査室】企画展関連講演会「吉原の本屋 蔦屋重三郎」講演:鈴木俊之教授
・台東区公式チャンネル【2025放送 大河ドラマの主人公を先取り】講演会「若き日の蔦屋重三郎と吉原」
https://www.youtube.com/watch?v=wVozVHwPTmw&t=2330s
